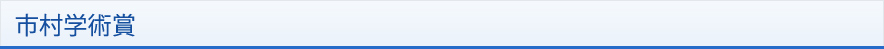|
高精細表示や高密度光記録用の光源、さらには高効率発光による省エネ推進とCO2排出量抑制のため、紫外線〜青・緑色の発光ダイオード(LED)・半導体レーザ(LD)開発が望まれていた。これらを実現する材料として、混晶化により広範囲に発光波長調整できる、窒素とガリウムやインジウム、アルミニウムの化合物であるIII族窒化物半導体がある(図1)。窒化インジウムガリウム(InGaN)混晶を活性層とする高輝度青色LEDが初めて発表された1993年、全世界の光半導体技術者が驚嘆した疑問は、「貫通転位という結晶欠陥密度がAlGaAs系LEDの1000万倍(図2)にも関わらず、なぜInGaNは強い光を出すのか? 更なる性能向上はできるか?」であった。
受賞者は、上記LEDや膜厚・組成・構造を人為制御した量子井戸に対してフェムト秒レーザを用いた時間分解分光法やナノメートルスケールの空間分解分光法等を用いて物性理論と併せた評価解析を行い、(1) Inを含む窒化物半導体混晶では、発光の源となる電子-正孔対(励起子)が、非発光性の欠陥に捕まるよりも速く「発光性の局在状態」に捕えられ効率高く発光再結合する「量子井戸励起子の局在発光」モデルを世界に先駆け提案し、(2) 後に、結晶中の点欠陥を検出できる唯一の手法である陽電子消滅測定結果と照らし合わせて、-In-N-In-のような原子サイズのIn-Nチェーン構造が正孔局在の正体であると示し(図3)、かような局在現象を他の欠陥性材料に利用する事を提案した。また、(3) 六方晶構造量子井戸に特有な「自発・圧電分極」による量子閉じ込めシュタルク効果を1996年にいちはやく指摘してLEDの高性能化とLD発振閾値低減の指針を与え、1998年には分極電場の排除を目的とした非極性面立方晶の利用を提案し、2007年、企業との共同研究で非極性m面InGaNレーザの室温連続発振を世界に先駆け成功した。
Inを含むIII族窒化物半導体混晶を用いた光デバイスは、LED表示や信号機はもとより、Blu-rayの読み取り書き込み用LD、そして白色LEDとそれを用いた照明に用いられており、今後も高色性・低消費電力照明として開発が進み、屋内外照明を置き換えてゆくであろう。

図1 III族窒化物半導体の格子定数とバンドギャップ・発光波長の関係

図2 InGaN量子井戸レーザの断面透過電子顕微鏡像

図3 InGaN 混晶における励起子局在のモデル図
(左:原子モデル模型、右:エネルギーを縦軸にとった模式図)
|