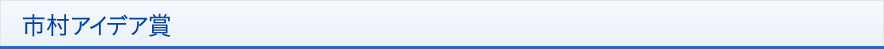受賞団体訪問
| 「生きる力」の育成、そのための「言語能力」の向上に力点 |
| 第43回(平成24年度) 団体賞奨励賞 愛媛県東温市立川内中学校 |
 |
応募した友だちを代表してインタビューに答えてくれた5人と、 後列右が石川校長、左が日野理科主任 |
初参加で団体賞に輝く 個人賞も3名が受賞 |
||
| 昨年記録した過去最高の215団体、17,093人(17,103件)を大きく上回る233団体、23,033人(23,041件)の応募があった第43回市村アイデア賞で、初参加にして団体賞奨励賞に輝いたのが愛媛県東温市立川内中学校です。個人賞でも朝日中学生ウイークリー賞はじめ3名が入賞しました。 東温市は平成16年、重信町と川内町が合併し誕生した都市近郊田園都市。全国住みよさランキングで愛媛県内第1位に選ばれ、東に隣接する県庁所在地・松山市のベットタウンとして発展、人口も増加しています。同校は昭和33年、川内町立川内中学校として開校。平成16年の市町村合併により東温市立川内中学校(以下川内中)と改称しました。現在平成23年に落成した新校舎で、「大同団結 共励切磋」の校訓の下、今年就任3年目を迎える第20代石川史朗校長と27名の職員の指導を受け、286名の生徒が元気に学んでいます。
|
戸惑ったり心配したがすでに次の構想へ |
||||||||||||||||||
全校生徒を代表して集まってくれたみなさんに聞きました。「初めて市村アイデア賞に応募したわけですが、どんな気持でしたか?」。
|
||||||||||||||||||
“全員に参加賞!”も応募促進の一手 |
||||||||||||||||||
|
「観察・実験は楽しく取り組むが、理科は難しいものと思い込んでしまっており、県の夏休み自由研究コンクールに参加する生徒はほんの数名だった」。生徒たちの当時の印象をそう語るのは、昨年赴任してきた理科主任の日野省吾先生。そこで地域の企業訪問で、例えば小さな技術が世界につながる、やればできるんだ、を実感させる。また昨年5月の皆既日食に際しては、全校生徒を体育館に集めてメガネを作り、早朝から運動場での観察会を行うなど、自分の手で新しいことをやろうという意欲の醸成に力を入れてきました。その日野先生が昨年、愛媛県教育研究協議会の支部委員会に市の理科委員長として出席し出会ったのが、新技術開発財団の担当者から説明を受けた市村アイデア賞です。 「表現することが苦手な生徒たちが、自分で楽しく発想し、書いてアイデアを説明する教育のツールとして"これだ"と直感。初めてなので動機づけのために、必ずしも作品を完成しなくていい、全員に参加賞がある、東京で表彰式だ、を強調し、ダメもとでチャレンジしようと応募を促しました」。生徒たちの反応は良く、全校の7割近い生徒の応募に至りました。 「来年はもっと頑張ろうと励ましながら、全校理科を、プレ市村アイデア賞応募の時間と位置付けています。生徒たちは以前よりずっと積極的に課題を受け止め、まじめに取り組んでくれています。個別の理科の実験も、理科室だけのものでない、日常生活を頭に描きながらやろうと指導しています」。 |
24年度は「気づき、考え、行動する」 |
||
|
「日野先生の主導で多くの生徒が参加し、受賞したことには、まず吃驚。同時に大変光栄に思っています」。そうおっしゃる石川校長が教育の柱に据えているのが「生きる力」。毎年、その年の教育目標をグランドデザインとしてまとめ、生きる力を育成しています。平成24年度のそれは「気づき、考え、行動する生徒を育てる」。生きる力の源とする自らの夢に向かい、「気づき」は自己理解=理想を持つ、「考え」は自己練磨=計画する、「行動する」は自己表出=果敢に実行すること。それが瞬時、また今日一日、あるいは何十年というそれぞれのスパンに対応して実践できる生徒に育てようと、あらゆる機会をとらえて呼びかけています。そのベースとして重視しているのが「言語能力」の向上。相手に伝える、それを聞く、活発に議論してさらに考え、最後に書いてまとめる。これをすべての授業に取り入れると共に、テーマを提示し3〜5名のグループで行う「話し合い活動」を展開しています。 最後に、石川校長は市村アイデア賞チャレンジについて、「グランドデザインの実現、言語能力の向上を推進するための具体的な活動になると評価しています。今回は驚きましたが、今後はその意義をより理解し、生徒たちの学びに活かしていきたい」と語ってくれました。
|