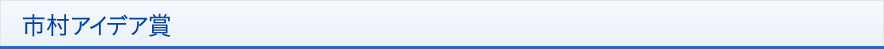受賞団体訪問
| 指導者の計画性と情熱に触発された生徒たちの自由な発想 |
| 第55回(2024年度)奨励団体賞 個人賞5作品受賞 千葉県八千代市立 勝田台中学校 |
 |
|
個人賞受賞の生徒たちと、熊谷俊彦校長(後列左)、近田博教諭(後列右)
|
地域との繋がりと伝統の「熱血祭」 |
|
2024年度の第55回市村アイデア賞では、全国から31,886件という多くの応募をいただきました。今回、千葉県八千代市立勝田台中学校(以下・勝田台中)が、初応募で奨励団体賞と市村アイデア優秀賞を含む5人の個人賞受賞という快挙を達成されました。 勝田台中は、千葉県北西部に位置する住宅団地の発祥の地として知られる八千代市にあります。1968年に創立され現在400名の生徒が学んでいますが、年々地域の高齢化が進み、生徒数も減少しているそうです。 そんななか、勝田台中では2023年度から地域の自治会と勝田台中の生徒の協同活動がスタートしました。年配の自治会員に交じり、お祭りなどの企画に積極的にアイデアを出しそれを実現しています。生徒たちも「自分が大人になった気がする」と誇らしげに話しているそうです。また、勝田台中には伝統の「熱血祭(運動会)」というイベントがあります。ここでは、各分団の分団長と応援団長を上級生の立候補者のなかから選びます。下級生は毎年活躍する先輩の姿を見ているので、この選挙の倍率は非常に高いそうです。こうした校内・校外での経験が、生徒たちに自主性や他者に対する思いやり、地域への視線を自然に育んでいるように感じます。 熊谷校長も「自分たちの考え・行動が社会や実際の生活のなかで結実していく経験が、今回の受賞にも影響しているかもしれません」と語ってくれました。 |
身近な問題から自由に発想する |
||||||||||
|
今回、市村アイデア賞への取り組みの中心となったのが、2023年度赴任された理科担当の近田教諭です。「市村アイデア賞では、学校という場ではできない生徒たちの表現や能力が発揮できます。身近なアイデアで、全員に活躍の場があるのです」と語る近田教諭。実は以前強豪校が揃う愛知県刈谷市で、市村アイデア賞に取り組んでいた経験者でした。 しかし指導の経験があるとはいえ、市村アイデア賞の認知度が低かった勝田台中では地道な根回しからスタートされたそうです。熊谷校長への賞の概要説明から始まり、校内だけでなく市内の理科部会など各所で熱心にアピールをされ、今年度の初応募に漕ぎ着けました。 市村アイデア賞は夏休みの宿題ですが、近田教諭は事前に過去の受賞作品やアイデアの取り組みのヒントなどの資料を作成され、他の理科担当の先生方の協力のもと、授業を行なったそうです。生徒たちはタブレットも活用しながら、身近な問題を自由にディスカッションしました。「野球部で飛んで行ったボールが見つからないことがある。という話題から、『ボールが落ちたところが光ればいい』『赤外線を当てると光るボールを作れば』など、現実的ではなくとも、問題を解決する面白い発想がたくさん出てくるんです」と近田教諭は授業の様子を語ってくれました。
|
||||||||||
自ら発見して解決する力の大切さ |
||||||||||
|
今回の受賞について「完全に子供たちの力」だと近田教諭は語ります。実は数年かけて個人賞の受賞をめざす計画だったそうです。 しかし、ここまで話を聞かせていただくと、経験のある指導者の計画的な事前準備と情熱。そして生徒たちの自由な発想が触発しあった必然の成果なのだと感じました。 「先人たちの知恵があって自分たちの社会や生活が豊かになっていることを、理科で学んでほしいと思います。そのうえで、ただ教科書の知識を学ぶのではなく、自分で問題を見つけて解決していくことの重要性を知ってほしいと思います。市村アイデア賞はそういう意味で非常に大切な経験になります。毎年続けていきたいです」と近田教諭。 熊谷校長は最後に「今はAIが発展していく時代ですが、新しく自分で発見してアイデアを生み出す力は、AIの分野ではないと思います。そういう力を生徒には身につけてほしい。これからの予測困難な社会を乗り切っていくためには、彼らの柔軟な発想が必要です。市村アイデア賞への挑戦で、それを伸ばしてあげられたら学校としては嬉しいですね」と語ってくれました。
|
||||||||||
個人賞受賞のみなさんにお聞きしました |
||||||||||
(取材日 2025年1月21日 千葉県八千代市)
|