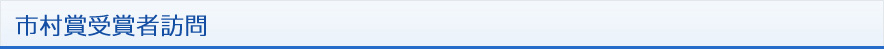これからの交通インフラ整備進展を睨み世界に誇る"鉄づくり"技術で起こした一大変革 |
長大吊橋の主塔に架け、ハンガーロープで結んだ橋桁を吊下げるメインケーブルは、直径5mm強の亜鉛めっき鋼線(ワイヤ)を平行に127本、6角形に束ねたストランドを、さらに直径約1mの太さに束ねたもの。ケーブル1本に合計約37000本のワイヤが使用され、長さは橋の全長間で継目のない数kmに及ぶ。
「開発した線材が国内で使用される機会は、ここ数十年中にはないだろう」と、開発に携わった技術者たちは言う。日本では、この線材を採用して造るセンタースパン(2本の主塔間の距離)の長い超ハイテン橋梁ケーブル用ワイヤ(1770MPa以上:1mm2当たり180㎏以上の重さの引張に耐えられる強さ)を要する吊橋や斜張橋等の長大橋建設は90年代末でほぼ一段落し、当面は需要が生じない見通しだからだ。しかし目を世界に向けた時見えるのは、90年代後半から2000年にかけ、中国やアジア等の新興国を中心に交通インフラの整備に伴う数多くの長大橋建設計画が立ち上がり、そこではワイヤの一層の高強度化と急増する需要への供給対応が急務となっている。当テーマは、そうした中、これからの交通インフラ整備進展を睨み、世界に誇る新日鐵住金の"鉄づくり"技術が起こした一大変革である。
|
高生産性・環境負荷低減で実績あるDLP設備を長大橋ケーブル用線材製造に適用させよう! |
橋梁ケーブル製造は従来、鉄鋼メーカーでの鋼材の熱間圧延・成型・コイリングによる線材製造⇒ワイヤメーカーでの線材熱処理(パテンティング)・伸線・めっきによるワイヤ製造⇒ケーブルメーカー工場でのストランド製作⇒架橋現場でケーブル化という工程を経る。この工程中、最も非効率なのがワイヤメーカーで金属組織を造り込むパテンティング工程。納入された線材を加熱後、"単線で鉛に浸漬する鉛浴"を施す方法で、鉛パテンティング(Lead Patenting:以下LP)と呼ぶ。LPでは1工場当たり月間処理量は1000トンと少ない上、加熱によるCO2の排出や鉛の使用による環境への影響も問題となっている。
そこで開発チームが目指したのが、85年に稼働させた独自のDLP(Direct in-Line Patenting:直接パテンティング)設備の適用による生産性の飛躍的向上。DLP設備は、線材の成型からパテンティング工程までを一貫させるもので、成型後の"コイル状の線材をそのまま溶融塩に浸漬する塩浴"で行う。ワイヤメーカーの鉛パテンティング工程を省き、1工場当たりの生産性を30倍高めると共に、CO2排出量7割削減と鉛フリー化を実現し、コンクリート建造物の補強鋼、ピアノ線製造等で実績を積んできた。しかし、このDLP線材®をこれからの長大橋ケーブルに適用させるには、越えるべき品質面の壁があった。
|
金属組織制御技術、現象解明、専用鋼種開発… "世界初"を次々と |
鉄は高温から低温にする際、金属組織が変化する変態という現象を起こす。パテンティングはその変態の中で硬度や延性が最も高い硬質パーライト組織を得る工程だ。LPでは線材の加熱後、単線で鉛に通すため均一な冷却処理ができる。一方、コイル状で塩浴に浸漬させるDLPでは、コイルが重なる両端部と、ばらけている中央部では冷却速度に差が出る。ここで生じるばらつきが線材の長手方向の材質ばらつきにつながってしまう。この難関を、コイリング時の強水冷により変態を起こす前の金属組織の結晶粒を微細化、変態を短時間化する最適金属組織制御技術を確立して突破。安定した品質を保証し2002年、世界初のDLP線材®の橋梁ケーブル適用を果たした。
品質面でぶつかった壁のもう一つは、塩浴による熱処理温度がLPの鉛浴より低い点だ。変態温度が低くなると線材表層に軟質ベイナイト組織が生成され、パーライト組織との混合組織を形成する。これはワイヤのねじりに対する強さ等の延性を低下させ、ケーブルのハイテン化を阻害する要因となっていた。開発チームはベイナイト生成過程をナノレベルで解析し、世界で初めて解明。2008年、圧延前の鋼材への合金元素B(ボロン)添加でベイナイト生成を抑制、さらにその効果を安定化させるTi(チタン)添加という緻密な成分設計により、高延性かつ高強度化が可能な橋梁用ワイヤ用DLP専用鋼種開発に至る。
|