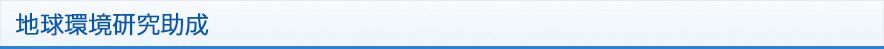地球環境研究助成04-04
触媒表面での物質移動の観測に基づいた水素燃料生成の反応制御
|
【 研究目的 】 |
| 光触媒を用いてバイオマス等から直接水素を生成する反応では、反応物から光触媒粒子表面の活性部位へのプロトン供給の過程が重要であり、表面における分子やイオンの反応過程を明らかにすることを目指した。バイオマスのモデル物質としてセルロースを用い、光触媒表面でのセルロース分子の酸化反応に伴うプロトンの生成と消費過程を、有機色素プローブ分子を用いた過渡分光法等により観測し、水素生成過程の評価および表面修飾による反応制御に発展させる。 |
【 研究方法 】 |
|
光触媒のモデル化合物として、酸化チタンおよびチタン酸塩のナノ粒子を既報の方法により合成し、その表面をホスホン基を有するシランカップリング剤および助触媒となる白金ナノ粒子で修飾した粉末および薄膜試料を作製した。さらにプローブとなる有機色素分子フルオレセインを吸着させた。 作製した薄膜試料について、過渡吸収法、時間分解蛍光法により、光触媒の光励起後サブピコ秒からナノ秒の時間スケールにおけるフルオレセインのプロトン解離平衡の変化を観測した。また、光電気化学測定とガスクロマトグラフ分析により、セルロース分解による水素生成反応を解析した。 ホスホン基修飾光触媒ナノ粒子の粉末試料に光照射を行い、水素生成反応を進行させ、ガスクロマトグラフ分析により水素の定量を行った。ホスホン基から光触媒表面の活性部位(助触媒)へのプロトンの移動と水素生成の促進を確認した。 |
【 研究成果 】 |
|
ピコ秒領域では、過渡吸収分光法により、酸化チタンの光励起にともなうフルオレセインの脱プロトン化に対して、セルロースの酸化分解により脱プロトン化の抑制、白金助触媒の効果により脱プロトン化の促進がみられた。すなわち、セルロースの酸化分解によるプロトン生成および助触媒上での還元反応によるプロトン消費の挙動を確認した。ナノ秒領域では、時間分解蛍光法により同様の過程を観測し、ナノ秒領域でもプロトン生成・消費過程が継続していることを確認した。酸化チタンは光酸化力が強い光触媒であり、白金はプロトン還元に有効な助触媒であることが知られているため、有機物の酸化分解によるプロトン生成および白金上でのプロトン消費が、光照射後ピコ秒の領域から効率よく進行することは、予想通りの結果であるといえる。 さらに光電気化学分析により、酸化チタン光触媒上において、定常的なセルロースの酸化分解により化学量論に相当する水素生成反応が進行することを検証した。緩衝能がありプロトンの授受を促進する役割のある官能基としてホスホン基を用い光触媒表面を修飾することにより、表面上の活性部位へのプロトンの供給過程を促進し、水素生成効率を向上させることに成功した。ホスホン基は周囲の酸性度の変化を抑制するとともに、プロトンの移動媒体として機能し、水素生成反応を制御できる可能性を示した。 |
【 まとめ 】 |
| 代表研究者は、光触媒表面でのセルロース分子の酸化反応に伴うプロトンの生成・移動過程、水素生成過程を過渡分光法により観測し、表面修飾による反応制御に発展させることを目指している。本研究ではその第一段階として、有機色素分子フルオレセインをプローブ分子として用い、プロトンの生成過程のダイナミクスをピコ秒からナノ秒にかけての時間領域で観測した。さらに、セルロースの分解による水素生成反応の進行状況を確認し、反応効率向上のために触媒粒子表面のホスホン基修飾により反応制御を可能にした。 酸化チタンは光酸化力が強い光触媒であり、白金はプロトン還元に有効な助触媒であることが知られているため、有機物の酸化分解によるプロトン生成および白金上でのプロトン消費が、光照射後ピコ秒の領域から効率よく進行することが明らかになった。今後は、酸化チタン以外の光触媒の活性を評価することにより汎用性の拡張が期待される。光触媒を用いてバイオマス等から直接水素を生成する反応について、光触媒粒子表面でのプロトン生成およびプロトン消費による水素生成過程を観測することに成功し、分光プローブ分子を用いた in situ での水素生成過程の評価および表面修飾によるさらなる反応制御の発展が期待できる。 |
【 地球環境保全・温暖化防止への貢献 】 |
| 太陽光エネルギーを利用した光触媒による水からの水素生成は、クリーンなエネルギー生産技術としてよく知られているが、これに加えバイオマス等の有機廃棄物からの直接水素生成についても、省プロセスで廃棄物処理とクリーンな燃料の生産を同時に達成できる点で、注目すべき技術となり得る。水分解による水素生成は、一般的に広く実用化利用を達成するにはまだ時間が必要であるのに対し、エネルギー的に有利な有機物分解は水分解より反応が高効率に進行するため、喫緊の対策としては、バイオマス等の利用による水素生成が有効である。光触媒や電極触媒により、水を含み燃焼熱利用が難しい有機物の分解・改質でも水素燃料の直接生成が可能になる。有機物分解は水分解より反応が高効率に進行し、理想的な完全循環が可能な水分解による水素生成を補完する水素燃料供給の役割を果たす。再生可能エネルギー開発の促進、クリーンエネルギーに関するSDG'sの達成の面から、地球温暖化対策に貢献する。 |
【 主な成果発表 】 |
||
|